古典に学ぶ二ホンミツバチの養蜂について
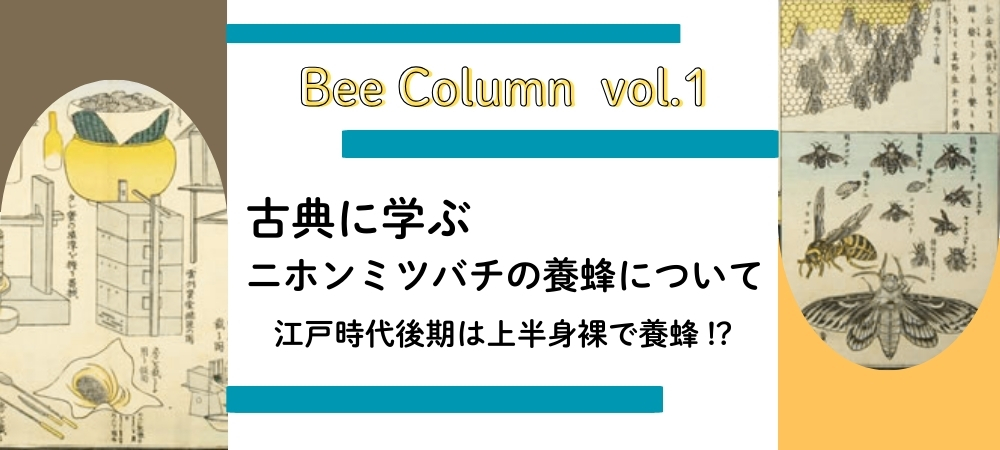
みなさん、「家蜂蓄養記(かほうちくようき)」という本をご存じでしょうか。
この本は、江戸時代に生まれた日本最古の養蜂書(日本みつばちを養蜂するための手引き書)です。著者である久世松庵(くぜしょうあん)は、江戸時代後期の紀伊国の医者、兼学者でした。
この手引書は、日本みつばちを養蜂する上で重要なポイントやミツバチの生態、観察に基づく推論を具体的に記されており、今日においても養蜂を学ぶ上で十分に通用する書であると言われています。(今回参考にした本は、「全訳 家蜂蓄養記 東繁彦 訳」です。引用部分もこちらの本の内容からですのでご承知おきください。)
当時(江戸時代後期)、養蜂は新しい産業であり、人々はまだ養蜂に対して正しい知識を持っていませんでした。そのため、薬商は、蜂蜜ではない何かを蜂蜜として売り、医者も不正確な医学書を頼っていたため、デタラメな知識を伝えていました。
医者である久世も、はちみつを薬用として利用していたため、この状況に苦慮していました。 そこで久世は、自らが養蜂をして正しい知識を多くの人に伝え、より広くミツバチが飼育されることで多くの蜂蜜が収穫されるようになれば、こうした状況が打開できるだろうと考え、本書を書き残しました。
さて、ここから、この本の中で面白い話がありましたので、紹介したいと思います。
「蜂の巣を切り取る時は、衣服を腰にまとい、上半身裸になる。そうしたとしても、少しも刺すことはない。むしろ、蜂は、衣の間に挟まった時に刺すものだから、服を着ていると却って刺されるのだ。そもそも蜂は人を刺すと死ぬので、性質上あまり刺さない」¹
なんと、久世は、蜂を扱う際は刺されないように上半身裸になることを推奨していました。ミツバチは服の間に挟まった時に刺すから、裸になれば刺されない…養蜂が始まってまだ間もない頃は自ら推論を立てていくしかありません。今では考えられない発想です。
また、巣の中を見る時の内検は、献上する宝物のように慎重さが必要だと言及しています。
「蜂にたかられても逃げたり払い除けたりせずに、しばらく身動きを止め、木か石のように思わせるように」² と助言しています。
ニホンミツバチはおとなしくあまり刺さない性格だとはいえ、現代の感覚からすると、上半身裸のあらゆるところにみつばちがいる状況で、平常心になれるはずもない…。
普通ならじっとなんてしていられないでしょう。今と大きく違う価値観に面白いなと思いました。(ただし、江戸時代末期になると、養蜂具が作られるようになり、手袋や面布も養蜂で使われるようになっていきました。)
ただ、久世は、論語「我、彼に善みせば、彼もまた我に善みするなり」を引用し、「相手に良くすれば、相手も自分に良くしてくれる」の精神で蜂に接する必要があると説いています。このような精神は、常に養蜂に対しての姿勢を問う洞察を得ることができます。みなさんも興味のある人は、現代との違いについて比べながら読んでみてください。
参考文献
1. 「全訳 家蜂蓄養記 東繁彦 訳 46項」 2. 「全訳 家蜂蓄養記 東繁彦 訳 48項」
